【徒然小噺】反転する加害者・被害者(2025.7.18)
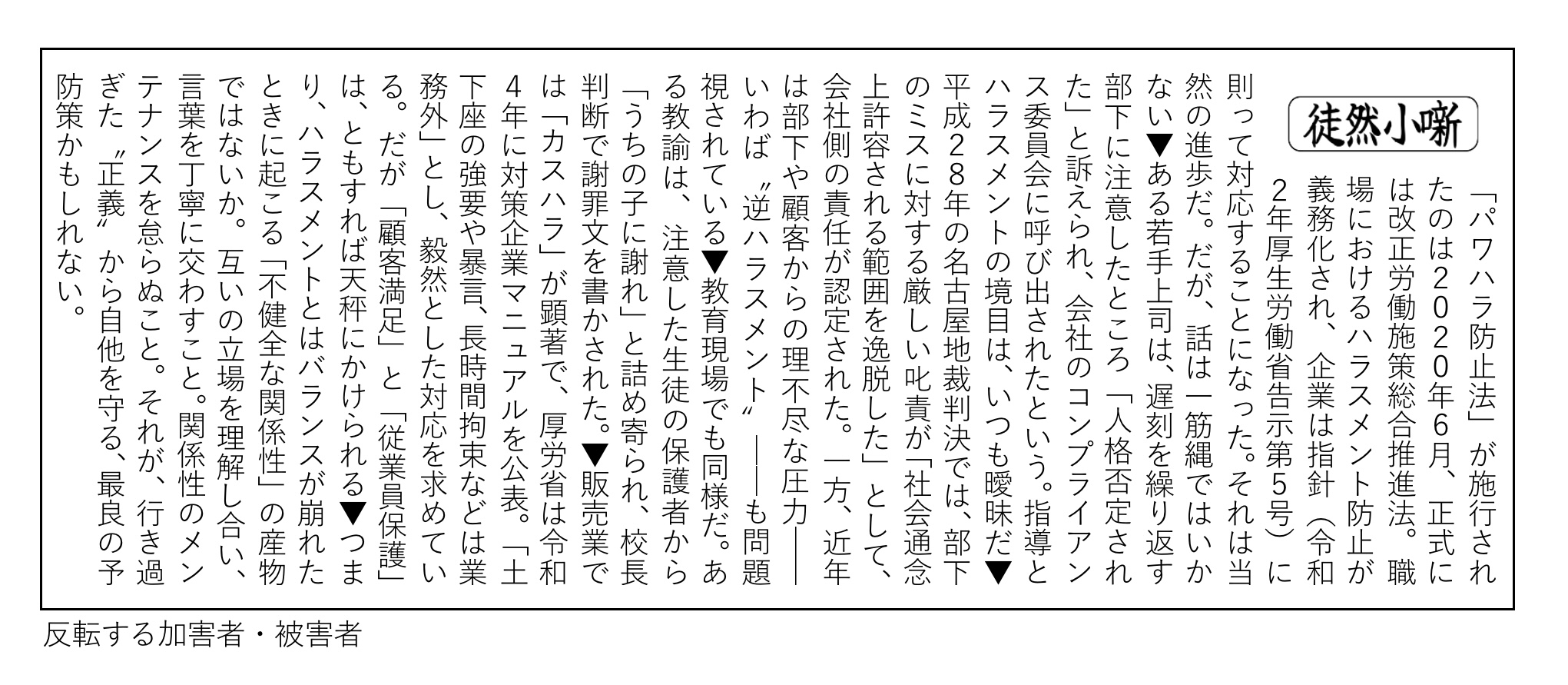
「パワハラ防止法」が施行されたのは2020年6月、正式には改正労働施策総合推進法。職場におけるハラスメント防止が義務化され、企業は指針(令和2年厚生労働省告示第5号)に則って対応することになった。それは当然の進歩だ。だが、話は一筋縄ではいかない▼ある若手上司は、遅刻を繰り返す部下に注意したところ「人格否定された」と訴えられ、会社のコンプライアンス委員会に呼び出されたという。指導とハラスメントの境目は、いつも曖昧だ▼平成28年の名古屋地裁判決では、部下のミスに対する厳しい叱責が「社会通念上許容される範囲を逸脱した」として、会社側の責任が認定された。一方、近年は部下や顧客からの理不尽な圧力——いわば〝逆ハラスメント〟——も問題視されている▼教育現場でも同様だ。ある教諭は、注意した生徒の保護者から「うちの子に謝れ」と詰め寄られ、校長判断で謝罪文を書かされた。▼販売業では「カスハラ」が顕著で、厚労省は令和4年に対策企業マニュアルを公表。「土下座の強要や暴言、長時間拘束などは業務外」とし、毅然とした対応を求めている。だが「顧客満足」と「従業員保護」は、ともすれば天秤にかけられる▼つまり、ハラスメントとはバランスが崩れたときに起こる「不健全な関係性」の産物ではないか。互いの立場を理解し合い、言葉を丁寧に交わすこと。関係性のメンテナンスを怠らぬこと。それが、行き過ぎた〝正義〟から自他を守る、最良の予防策かもしれない。
※実際に受けた質問や相談に関して向き合った諸々を「新聞コラム形式」で綴りました。
※投稿者:山田留理子(特定社労士)
≪ 【徒然小噺】退職代行という文化の風景 | 【徒然小噺】パート勤務時に発生した年休は、正社員登用後はどう扱われるの? ≫
