【徒然小噺】会議が多すぎて、仕事が進みません!(2025.8.7)
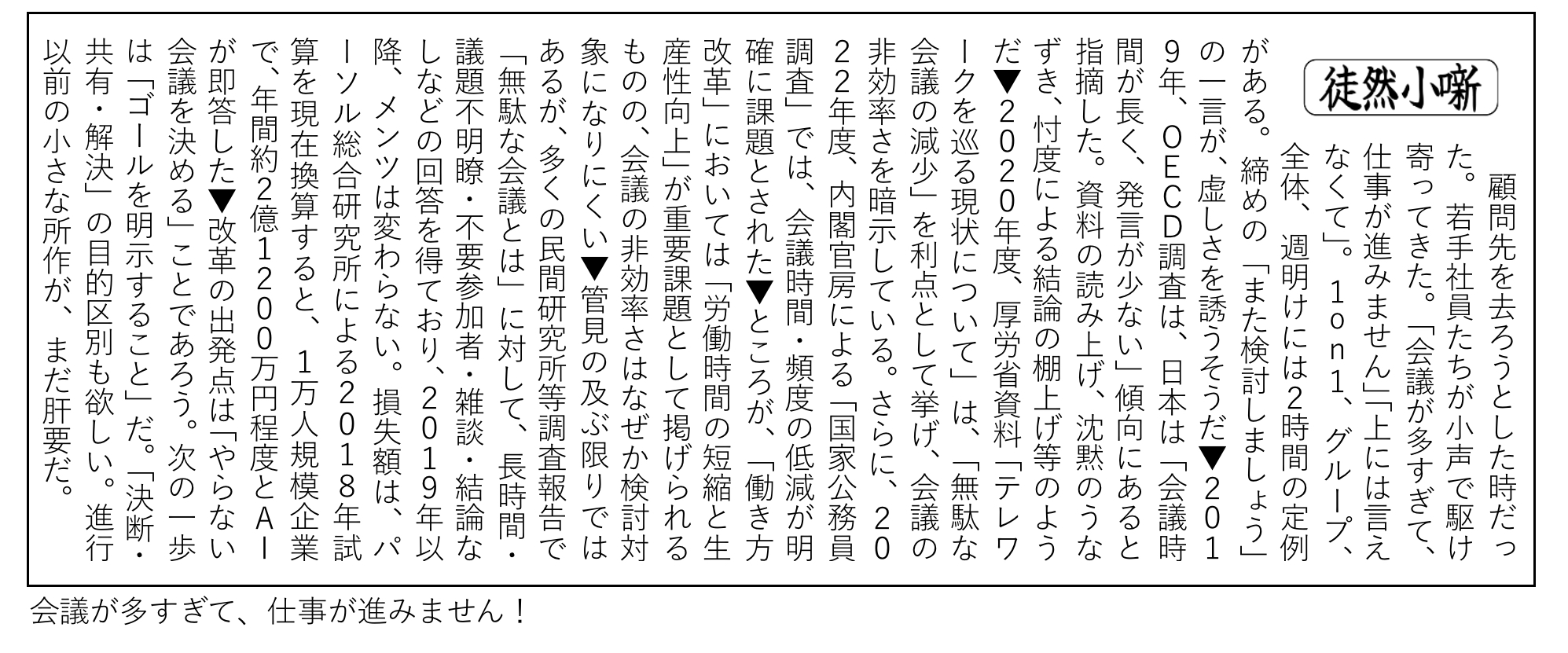
顧問先を去ろうとした時だった。若手社員たちが小声で駆け寄ってきた。「会議が多すぎて、仕事が進みません」「上には言えなくて」。1on1、グループ、全体、週明けには2時間の定例がある。締めの「また検討しましょう」の一言が、虚しさを誘うそうだ▼2019年、OECD調査は、日本は「会議時間が長く、発言が少ない」傾向にあると指摘した。資料の読み上げ、沈黙のうなずき、忖度による結論の棚上げ等のようだ▼2020年度、厚労省資料「テレワークを巡る現状について」は、「無駄な会議の減少」を利点として挙げ、会議の非効率さを暗示している。さらに、2022年度、内閣官房による「国家公務員調査」では、会議時間・頻度の低減が明確に課題とされた▼ところが、「働き方改革」においては「労働時間の短縮と生産性向上」が重要課題として掲げられるものの、会議の非効率さはなぜか検討対象になりにくい▼管見の及ぶ限りではあるが、多くの民間研究所等調査報告で「無駄な会議とは」に対して、長時間・議題不明瞭・不要参加者・雑談・結論なしなどの回答を得ており、2019年以降、メンツは変わらない。損失額は、パーソル総合研究所による2018年試算を現在換算すると、1万人規模企業で、年間約2億1,200万円程度とAIが即答した▼改革の出発点は「やらない会議を決める」ことであろう。次の一歩は「ゴールを明示すること」だ。「決断・共有・解決」の目的区別も欲しい。進行以前の小さな所作が、まだ肝要だ。
※実際に受けた質問や相談に関して向き合った諸々を「新聞コラム形式」で綴りました。
※投稿者:山田留理子(特定社労士)
